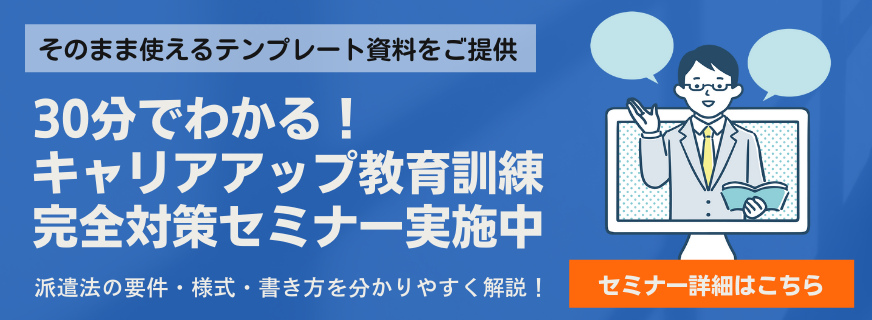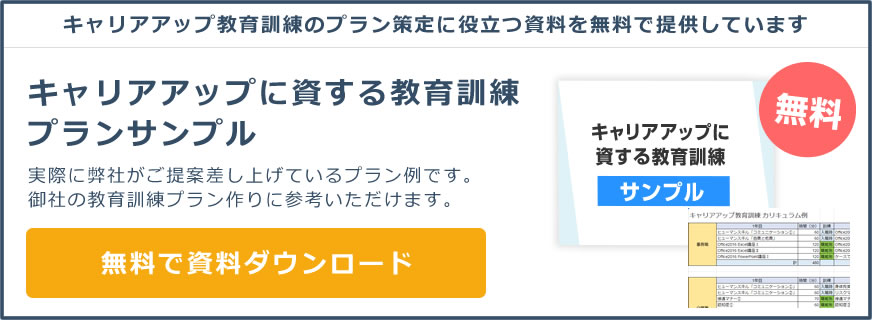雇用調整助成金の対象となる教育訓練は?【特例措置対応】
新型コロナウイルス感染症の影響で社会情勢は大きく変化し、苦境に立たされている業界や企業は少なくありません。 その結果やむを得ず休業者が出ることがありますが、「雇用調整助成金」という制度をうまく活用することで、補助金を受け取りながら休業中の労働者に対して教育訓練をすることができます。 この記事を読んでいただくことで、雇用調整助成金とはどのようなものなのか、また休業中にどのような教育訓練をすべきなのか分かります。 また、新型コロナウイルス感染症の影響によって新たに施行された特例措置についても解説します。目次
雇用調整助成金とは
主に教育訓練を行う場合を想定し、「雇用調整助成金」の概要を説明します。 今回の特例措置で雇用調整助成金の受給範囲は広がっているので、休業中の労働者がいる場合には積極的に活用したい制度となっています。休業中の労働者がいる企業を対象にした支援制度
雇用調整助成金とは、経営状況の悪化等を原因として休業している労働者が、雇用関係を維持できるようにするために支給されるものです。 経営の悪化等が原因で企業に休業者が生じた場合、休業者には平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払うことが義務づけられています。 しかし、資金繰りがうまくいかない企業ではその休業手当すら払うことができず、労働者を解雇してしまうケースもあります。 そうした事態を避け、休業中の労働者を守るために作られたのが雇用調整助成金制度です。 企業規模や雇用の状況により給付金額の上限は異なります。教育訓練と雇用調整助成金
休業中労働者に対して教育訓練を行うことで、雇用調整助成金が加算されます。これは厚生労働省が、休業期間を活用した労働者のスキルアップを積極的に勧めているためです。 助成金加算の対象となる教育訓練の幅は広いため、業界や各個人に求められているスキルなどをもとに、多様な教育を行うことができます。 この教育訓練については、後ほど詳しく説明します。新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
新型コロナウイルス感染症の蔓延が原因で業績が悪化した企業は多く、その結果休業を余儀なくされた従業員はかなりの数に上ります。 そのため、厚生労働省は特例措置として雇用調整助成金の条件緩和と支給額の引き上げを発表しました。 2021年12月現在、この特例措置は12月末まで継続し、2022年3月まで延長する予定があることが発表されています。 未申請の企業もこれから申請を行うことができるので、厚生労働省のホームページから詳細をご確認ください。 そして教育訓練に関する加算額も同様に引き上げられ、これまで1人1日あたり1,200円だった加算上限額は、中小企業で2,400円、大企業で1,800円となりました。 また、教育訓練実施日の就労はこれまで認められていませんでしたが、特別措置施行後は半日訓練・半日就労ができるようになりました。

雇用調整助成金申請の流れ
続いて、雇用調整助成金を申請する際の具体的な手順をご説明します。 申請時にはいくつかの書類が必要となり、注意すべきポイントもあるため、事前に準備をしておくことが大切です。申請の大まかな流れ
雇用調整助成金の給付を受ける際には、いきなり申請だけをするのではなく、事前の準備が必要不可欠です。 ここでは大まかなステップを4つに分けてご紹介します。 ①教育訓練を通して得られる効果を想定する まずは休業者に対して教育訓練を行うことでどのような効果が得られるのか想定した上で、受講目的を明確にします。 しっかりと目的を設定することで、教育訓練を受ける休業者自身だけでなく雇用を行っている企業側も教育の方針を立てやすくなります。 業界や業種によって有効な教育訓練は異なります。自社の従業員に対してどのような教育訓練が最適なのか情報収集をしましょう。 ②具体的な訓練の内容を決める 教育訓練の最終的なゴールが決まったら、次は具体的な内容を決めていきます。 この段階でカリキュラムを作成しておけば、後々スムーズに教育訓練や助成金の申請が行えるでしょう。 また、教育訓練の実施場所によって申請書類が異なるため、事前に研修場所(社内・社外いずれか)や外部の教育機関の決定をしておきます。 ③計画届を労働局に提出する 教育訓練の計画が決まったら、計画届を作成して各都道府県の労働局に提出します。 管轄のハローワークにも提出することができます。 ④教育訓練を実施し、雇用調整助成金の申請を行う 実際に休業者に対する教育訓練を行います。その後申請書類を記入し、労働局に提出します。ハローワークでも書類の受理が可能です。 ここまでが申請までの大まかな流れです。 大切なのは事前に明確な目標と無理のない計画を立てることです。 休業者の視点に立ち、どのような能力を高めれば今後の業務で活きるか考えなくてはなりません。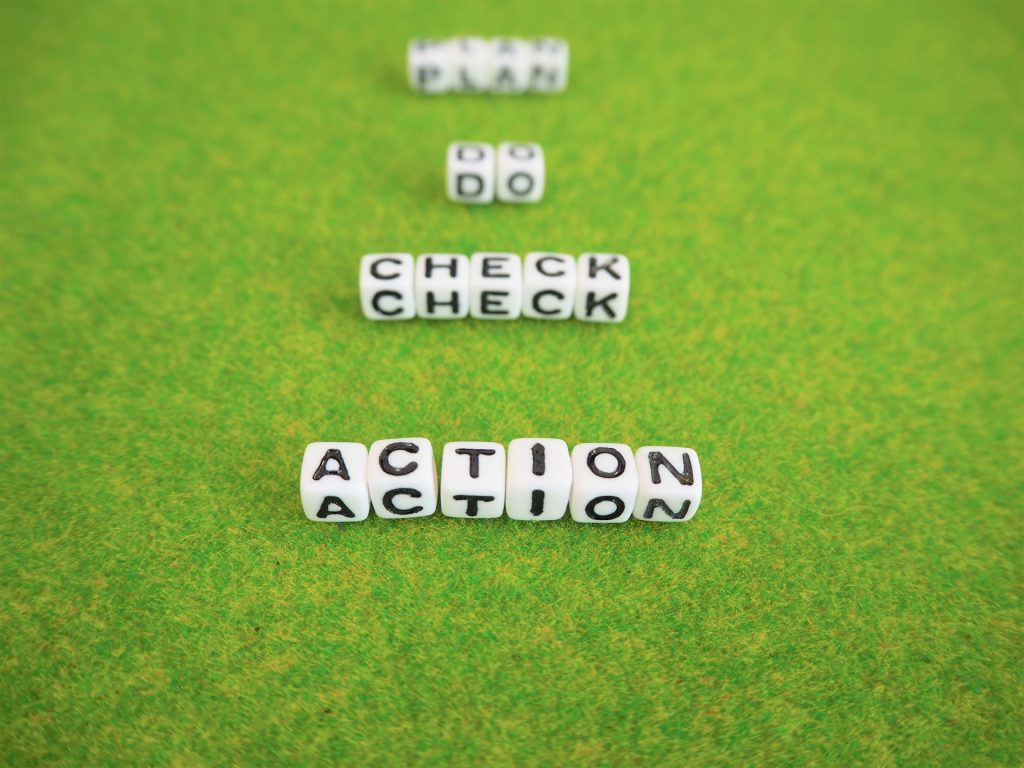
必要な書類
特例措置中に教育訓練を実施し、雇用調整助成金の申請を行う場合、必要な書類は下記の通りです。 書類の作成に時間がかかるケースもあるので、申請時期から逆算して早めに書類の作成に取りかかりましょう。- 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
- 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
- 休業・教育訓練計画一覧表
- 休業協定書・教育訓練協定書
- 事業所の状況に関する書類
- 教育訓練の内容に関する書類
教育訓練を実施する際に気をつけるべきこと
教育訓練を行い雇用調整助成金の申請をする場合、気をつけなければならないことがあります。 それは教育訓練をどこで行うのか明確にしておくこと。 教育訓練を行う場所は事業所の内外どちらも想定されます。それぞれで申請時に提出する書類が異なるため間違えないよう注意しましょう。ちなみに、弊社のeラーニングを活用の場合は「事業所内訓練」として扱われるため、「支給申請合意書(様式13号)」は記入不要となります。どんな教育を行えば良い?オンラインでも大丈夫?
一口に教育訓練と言っても、様々な種類があります。 訓練内容はもちろんですが、研修を行う場所や外部の教育機関に依頼するかどうかなど、たくさんの選択肢があります。 そして中には助成金給付の対象とならないものもあります。 ここでは、どのような教育訓練を行えばよいのかを解説していきます。雇用調整助成金の給付対象となる教育訓練とは
基本的に、雇用調整助成金の申請時に教育訓練として認められるのは、各業務に従事する労働者に必要な教養以上のスキルを身につけるためだと判断されたものです。 たとえば、飲食業や宿泊業、タクシー運転手として必要な教養を超えた英語研修を受ける場合にはこの対象となります。 一方で新入社員研修や法令で定められている教育など、業務上必要不可欠な教育は対象外です。特例措置による助成金対象範囲の拡大
上記で必要不可欠な教育は助成金の対象外だと紹介しましたが、今回発表された特例措置でその条件は緩和されています。 特例措置で教育訓練だと認められるようになった訓練には、以下のようなものがあります。- 自宅で行う訓練(eラーニング等)
- マナー研修、新入社員研修、メンタルヘルス研修など、どの業界でも共通して必要になる教育
- 過去に行った教育訓練を再度実施
研修内容によっては教育訓練として認められない場合も
行った研修が教育訓練として認められるかどうかは、企業や職種に必要なものかどうかで判断されます。そのため、一概に「この研修は認められる」「この研修は認められない」とは言えません。語学研修を例に挙げると、外国語を業務の中で頻繁に使う業種では教育訓練として認められる可能性が高くなりますが、全く外国語を使うシーンがない業種の研修としては認められない場合があります。 そのため、既存の業務や今後の事業展開を踏まえ、どのような研修が最適か見極める必要があります。積極的に進むeラーニングの活用
 今回の特例措置により、eラーニングで行われる教育訓練も雇用調整助成金給付の対象となりました。
コロナ禍で集合研修の実施が難しい今、eラーニングを活用する企業は増えてきています。
受講者は気軽に自分に合った教育訓練を受けることができますし、管理者も受講者がどのようなコンテンツを視聴したのか管理しやすくなっています。
当社でも、雇用調整助成金の申請に対応したeラーニングコンテンツを多数ご用意しています。
eラーニングに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
今回の特例措置により、eラーニングで行われる教育訓練も雇用調整助成金給付の対象となりました。
コロナ禍で集合研修の実施が難しい今、eラーニングを活用する企業は増えてきています。
受講者は気軽に自分に合った教育訓練を受けることができますし、管理者も受講者がどのようなコンテンツを視聴したのか管理しやすくなっています。
当社でも、雇用調整助成金の申請に対応したeラーニングコンテンツを多数ご用意しています。
eラーニングに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
この機会を活用して充実の教育を!
新型コロナウイルス感染症の蔓延に起因する企業の経営状況悪化により、多くの業界や業種において休業者が出てしまっています。 もちろん、経営者は極力休業中の労働者を生み出さないようにしなければなりませんが、休業中の労働者への教育訓練にも力を入れるべきだといえます。 雇用調整助成金を活用することで、労働者に対して効果的な教育訓練を行うことができます。教育訓練を通して労働者がスキルアップできれば、労働者自身にも企業にも多くのメリットがもたらされます。 この機会に休業中の教育訓練を見直してみませんか? 当社では休業者を対象にしたeラーニングを展開しています。ぜひご活用ください!
キャリアアップ措置とは?他社との差別化ポイントまでご紹介
すべての派遣事業者は労働者派遣法(以下、派遣法)に則って派遣事業を行わなければなりませんが、中でも「キャリアアップ措置」について、なにをすべきか分からないという声をいただくことがあります。 そのため、今回は特に派遣労働者のキャリアアップという観点から、キャリアアップ措置について説明を行います。 これから派遣事業を始める場合にも、事業の中でキャリアアップ措置に関する悩みを抱えている場合にも参考にしていただける記事となっています。1.キャリアアップ措置とは
 具体的な方策を挙げる前に、一度キャリアアップ措置について整理してみましょう。
そもそもキャリアアップ措置とはどのような意図で、どのようなことを求めているものなのか解説していきます。
また、この措置の対象者や必要な訓練についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
具体的な方策を挙げる前に、一度キャリアアップ措置について整理してみましょう。
そもそもキャリアアップ措置とはどのような意図で、どのようなことを求めているものなのか解説していきます。
また、この措置の対象者や必要な訓練についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
1-1.派遣労働者がキャリア形成をするための教育体制のこと
キャリアアップ措置を簡単に説明すると、「派遣労働者のためのキャリアに関する教育を施すこと」となります。派遣労働者として業務に従事する中で、本人の希望や適性に沿ったキャリアを歩んでいくために最も重要なのは、教育と言っても過言ではありません。 そして適切な教育を行い、必要があればキャリアコンサルティングを行うことは派遣事業者の役目です。 そのため、派遣法ではキャリアアップ措置が義務づけられており、段階的かつ体系的な教育訓練の実施と、キャリアコンサルティングの実施が求められています。1-2.キャリアアップ措置の対象者
措置の対象者となるのは、派遣事業者において雇用されている派遣労働者です。 そしてキャリアアップ措置に関する義務は派遣元だけでなく、派遣先にもあります。 それぞれ行うべき措置は異なるので、どちらの対象となっているのかを事前に把握しておきましょう。 派遣元と派遣先には、それぞれ以下のような措置が義務づけられています。1:派遣元の義務
- 労働局への教育訓練計画の提出
- 計画的な教育訓練の実施
- 希望者へのキャリアコンサルティングの実施
- 教育訓練などの実施状況の報告
- 派遣元管理台帳などにおいて教育訓練の実施状況を記録すること
2:派遣先の配慮義務・努力義務
- 派遣労働者が希望した場合には、対象者へ教育訓練を受けられるよう可能な限りの協力や配慮を行うこと
- 派遣元の求めに応じ、派遣労働者のキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元へ提供すること
1-3.キャリアアップ措置に関する注意点
特に派遣元がすべき措置は多いですが、その中で気をつけなければならないことがあります。 厚生労働省が定めている条件をもとに、いくつか注意すべきポイントをご紹介します。- キャリアアップ措置は、「派遣事業元に雇用されている派遣労働者全員」が対象でなければならない
- 教育訓練は有給かつ無償で行われなければならない
- 雇用期限がない派遣労働者に対しては長期的なキャリアアップを視野に入れたキャリアアップ措置を行わなければならない
2.具体的にはなにをしたらよいか
キャリアアップ措置の概要を把握したところで、より具体的な内容に移っていきましょう。 今回は特に派遣事業元が行うべきことについてまとめています。2-1.キャリアアップ教育訓練実施計画を労働局に提出する
2015年の派遣法の改正以降、派遣事業者は「キャリアアップに資する教育訓練」の計画を策定し、提出しなければならなくなりました。 基本的にはキャリア形成を目的とした教育訓練を、主に「どの段階で」「どのように」「なぜ」行うのかまとめ、教育訓練の実施計画として労働局に提出することになります。 入社年次ごとの教育内容と、その内容で教育を実施することの目的をまとめるのが一般的です。 労働局に認めてもらえれば良いという観点ではなく、派遣労働者に対して真摯に向き合い、明確に記載を行うことが重要です。2-2.派遣労働者に対して教育訓練を実施する
計画の策定と提出が終わったら、その計画に従って教育訓練を行います。 基本的なビジネスマナーから専門的な技能教育まで、年次や業種によって内容はさまざまです。 ただ忘れてはいけないのは、どれもすべて派遣労働者のキャリアアップのための教育であるということです。 会社のためではなく、あくまで個人のキャリアのためであるということは念頭に置いておく必要があります。2-3.希望の場合にはキャリアコンサルティングを行う
派遣労働者からキャリアコンサルティングの希望があった場合、派遣事業者はそれに応じなければなりません。 キャリアに関する相談を受ける担当者についても要件が定められており、キャリアコンサルタントとしてふさわしい人を配置する必要があります。 また事務所内に相談窓口を設けるだけでなく、メールや電話、専用フォーム等からもキャリアに関する相談を受け付けられるようにすることが求められているため、適切な受付手段の整備と周知は必須になっています。3.キャリアアップ訓練はどのように行うべき?
 キャリアアップ教育訓練の実施計画をもとに教育訓練を行うと先述しましたが、実際どのようなことを念頭に置きながら訓練を行うべきなのでしょうか。
また、現地での集合研修ができない昨今の状況下で派遣事業者ができることはなにか、解説します。
キャリアアップ教育訓練の実施計画をもとに教育訓練を行うと先述しましたが、実際どのようなことを念頭に置きながら訓練を行うべきなのでしょうか。
また、現地での集合研修ができない昨今の状況下で派遣事業者ができることはなにか、解説します。
3-1.従業員のためになる教育訓練を
まず絶対に押さえておかなければならないのは、「派遣労働者のことを考える」ということです。 実施計画を形だけのものにしないためにも、実施する教育訓練の質にはこだわるべきでしょう。 業界や受講者のレベル等によって訓練の内容は変わることが考えられますが、社内でノウハウを持った人がいなければ外部に委託するのも手です。 「派遣の学校」でもキャリアアップのための教育コンテンツを多数用意しています。 ぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。3-2.教育訓練で他社との差別化が可能
教育訓練の実施は全事業者で必須となりましたが、実際に実施されている訓練の質は派遣会社によってさまざまだといえるでしょう。 必要最低限の教育訓練でも基準さえ満たしていれば労働局に認めてはもらえますが、それでは本当の意味でのキャリアアップ教育にはなっていないといえます。 反対に、充実した教育プログラムを用意しそれを広く周知することで、他の派遣会社との差別化ができます。 それほど派遣事業者におけるキャリアアップ措置の重要性は非常に高いのです。3-3.eラーニングの活用も進む
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、派遣労働者を集めて研修を行う「集合研修」は最近では行われなくなってきています。 代わりに積極的に活用されるようになってきたのがeラーニングでの研修です。 eラーニングの活用で、これまで教育担当者の方が頭を悩ませていた、場所や時間の問題が解消します。 eラーニングを導入したいけれどコンテンツの内製は難しいという場合には、ぜひ「派遣の学校」までご相談ください。 多様な業種に対応した高品質なコンテンツを取りそろえておりますので、現場の負担をかけずに充実したキャリアアップ教育訓練を行うことができます。3-4.キャリアのコンサルティングも併せて行うことで効果アップ
多くの派遣事業者では教育訓練に重きを置き、キャリアコンサルティングについては力を入れる余裕がないと言うのが実情のようです。 ただ、派遣労働者のキャリアのことを考えると、キャリアコンサルティングは積極的に実施すべきだといえます。 この先のキャリアプランが明確に決まっていて、そのためになになにをすべきか自分自身で明確に理解できている人は少ないものです。 派遣会社でどのようにキャリアを積むべきか本人の意向に沿って考えられるようなコンサルティングができれば、従業員は安心して働くことができます。 そうした観点からキャリアコンサルティングの質も教育訓練同様、他社との差別化ポイントだといえます。4.従業員のことを考えたキャリアアップ措置で他社との差別化を!
これから働く派遣会社を選ぶポイントとして、そこで得られるスキルやキャリアステップを重視する人は非常に多くなっています。 そのため、派遣事業者がキャリアアップ措置に力を入れるのは必要不可欠といえます。 従業員のキャリアのことを真剣に考え、そのための手段としてキャリアアップ措置を行っていれば、自ずと人が集まる会社になるはずです。 「派遣の学校」ではこうした派遣会社におけるキャリアアップ措置に関するご相談を受け付けております。 是非お気軽にご連絡ください。
人材派遣会社を作るにはどんな資格が必要?要件や必要書類を解説!
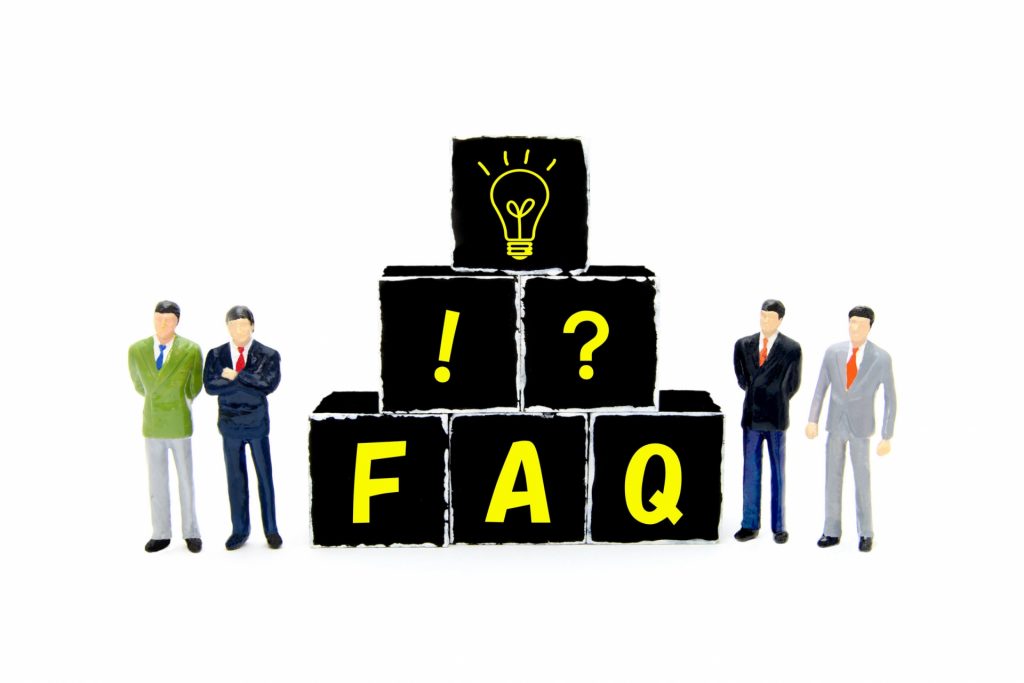 派遣事業の市場規模は、2025年1月の雇用者数5,822万人、前月から16万人減少しつつも、2024年同月からは73万人増となりました。
派遣社員は159万人、前月から6万人増、2024年同月からも9万人増となりました。
売上予測は「約4.8兆円類推」から「10兆円を超える」予測までさまざまです。
この大きな市場をもつ派遣事業の可能性は今後も広がっていくことが予想されますが、事業を始める際には厚生労働省の認可を取得する必要があります。
そして認可を得るためにはいくつかのステップがあり、人材派遣で起業をする際には事前準備が必須だといえます。
この記事では主に人材派遣会社を設立するための必要資格や要件、必要書類について解説を行います。
派遣事業の市場規模は、2025年1月の雇用者数5,822万人、前月から16万人減少しつつも、2024年同月からは73万人増となりました。
派遣社員は159万人、前月から6万人増、2024年同月からも9万人増となりました。
売上予測は「約4.8兆円類推」から「10兆円を超える」予測までさまざまです。
この大きな市場をもつ派遣事業の可能性は今後も広がっていくことが予想されますが、事業を始める際には厚生労働省の認可を取得する必要があります。
そして認可を得るためにはいくつかのステップがあり、人材派遣で起業をする際には事前準備が必須だといえます。
この記事では主に人材派遣会社を設立するための必要資格や要件、必要書類について解説を行います。
目次
1. 人材派遣業とは
そもそも人材派遣業とはどのような業種なのでしょうか。 「従業員を集め、人材を必要としている場所への派遣を行う」という漠然とした認識をお持ちの方も多いかもしれませんが、実際はもう少し細かく定義がされています。 人材派遣業に似た業種の「有料職業紹介事業」との違いを含めて解説を行います。1-1. 自社で雇用した社員を派遣する事業
人材派遣業のベースとなるのは、社員を雇用して人材として派遣を行うというスタイルです。 人材派遣に関する法律の労働者派遣法では、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」が人材派遣であると定義されています。 つまり、派遣会社に雇用された従業員をその会社以外の会社で労働に従事させるのが人材派遣業の基本となっているということです。1-2. 有料職業紹介事業との違い
人材派遣業と似たような業種に「有料職業紹介事業」というものがあります。 これは人材を集めて仕事をあっせんし、仲介手数料を派遣先企業から得るという業種です。 一見すると同じような業種に思えますが、最も大きな違いは雇用先がどこであるかという部分にあります。 人材派遣業では従業員は「派遣元」の会社に雇用され、有料職業紹介事業では「派遣先」の企業に雇用されます。 そのため、これから起業を考えて入る場合には行う事業がどちらに分類されるのか明確にしておく必要があります。1-3. 人材を派遣できる業種・できない業種
多様な業界において人材派遣会社からの従業員派遣が行われていますが、その一方で人材派遣を行うことができない業種も存在します。 下記がその一例で、どれも高度な知識や技術・資格を要するものです。- 弁護士や司法書士
- 医療関係業種(医師や看護師など)
- 建設作業や土木作業に従事する職種
- 港湾運送業務を伴う職種(船内荷役や検査業務などに従事する場合)
- 警備に関連する業務
2. 派遣事業を始めるにあたって必要な資格・許可とは
 派遣会社は、誰しもが作ろうと思った時に作れるわけではありません。
事業を始める前に必ず取得しなければならない許可や資格があります。
資格の取得に際して実務経験も必要となるため、事前の確認と準備を怠らないようにしましょう。
派遣会社は、誰しもが作ろうと思った時に作れるわけではありません。
事業を始める前に必ず取得しなければならない許可や資格があります。
資格の取得に際して実務経験も必要となるため、事前の確認と準備を怠らないようにしましょう。
2-1. 必要な資格:派遣元責任者
派遣事業を始めるためには、派遣元責任者講習を受講して派遣元責任者になる必要があります。 必要な資格はこの一つですが、実際に派遣元責任者として職務を行う場合には3年以上の雇用管理経験が求められます。 具体的には企業で人事や労務の担当者を3年以上経験するか、職業安定行政や労働基準行政で3年以上業務に従事するなどの経験が必要です。 なお、これらの経験は20歳時点から起算されるため、実務を20歳未満から始めた場合には要注意です。2-2. 必要な許可:労働者派遣事業許可
派遣元事業責任者となったら、厚生労働省から「労働者派遣事業許可」という認可を取得することになります。 2015年の労働者派遣法の改正により、すべての派遣事業者は許可を得て事業を行わなければならなくなりました。 また、初回は3年、それ以降は5年ごとにこの許可の更新をしなければ事業を継続することはできなくなります。 派遣事業で起業する上で避けては通れない許可なので、頭に入れておきましょう。 この許可を取得するための要件については、次の章で詳しく紹介します。3. 労働者派遣事業許可を得るための要件
派遣会社を設立する際には、最終的には厚生労働省の認可(労働者派遣事業許可)の取得を目指すことになりますが、そのために満たさなければならない要件がいくつもあります。 ここでは要件を五つに大別し、それぞれの概要をご紹介します。 現状との比較やこれからの目標策定にお役立ていただければ幸いです。 各要件のポイントはこちらの記事でより詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。3-1. 資産に関する要件
厚生労働省への許可申請を行う際に最低限満たさなければならない資産面での要件は次の三点です。・基準資産額が2,000万円以上ある ・資産から負債を除いた額が負債の7分の1よりも多い ・資産のうち1,500万円以上が現金である
基準資産額が2,000万円以上ある
基準資産額とは、基本的には(資産総額)−(負債総額)のことです。 他に差し引くものもありますが、ここでは割愛させていただきます。 派遣時事業者として認可を受ける場合には、この基準資産額が2,000万円以上であることが必須となります。 「起業の際には資本金が2,000万円以上あれば良い」と言われることがありますが、基準資産額と資本金は異なるものです。 算出の結果、資本金は2,000万円以上あるが基準資産額が2,000万円を下回っているという場合もあります。 事前に正しい算出方法で基準資産額を求め、基準を満たしておく必要があります。 ちなみに、複数の事業者を設立する場合も基準資産額を合算することはできないため、2,000万円が事業所ごとに必要となります。資産から負債を除いた額が負債の7分の1よりも多い
基準資産額が基準を満たしている場合でも、負債が多い場合には要注意です。 (資産)から(負債)を引いた金額が負債総額の7分の1よりも多くなっているか、しっかり確認しておきましょう。資産のうち1,500万円以上が現金である
現金の資産が1,500万円を下回っている場合も、認可を得ることができません。 「現金の資産」とは貸借対照表でいうところの「現金」と「預金」を足し合わせたもの。 すぐにお金として動かすことができるお金が1,500万円以上なくてはならないのです。3-2. 派遣元責任者に関する要件
派遣元責任者にも基準が設けられています。 下記基準が代表的なものです。・未成年者でなく、住所が一定であること ・良好な健康状態であること ・他人を不当に拘束・束縛しないこと ・公共の場にふさわしくない業務でないこと ・責任者自身が派遣労働者として労働しないこと ・名義借りではないこと ・申請時点で派遣元責任者講習の受講後3年以内であること ・外国人の場合、在留資格があること ・労働者派遣法6条の第1号から第12号に定める欠格事由に該当しないこと
労働者派遣法の「欠格事由」には、暴力団の構成員であることや破産している場合が該当します。 責任者にこの欠格事由に該当する事実がなかったとしても、法定代理人や役員が該当する場合には認可を受けることができません。3-3. 事業所の広さや立地に関する要件
続いて、事業を行う場所に関する要件です。 申請時には必ず労働局による現地調査が行われますが、下記要件をすべて満たしていなければ事業所としては認められません。・事業で利用する面積が20平方メートル以上あること ・使用目的が賃貸借契約書の目的と一致していること(事務所用途であること) ・別の法人が同じ場所で業務を行っていないこと ・個人情報を守ることができる環境が整っていること ・風俗営業店の密集エリアに位置していないこと
事業所の面積については、「事業で利用する」部分が20平方メートル以上なくてはなりません。事業に関係ない部分の面積は含まれないため、実際の事業所の総面積はもう少し大きくなることがほとんどです。 また、風営法で規制されている風俗営業店が付近に密集している場合、事業所の立地として不適当だと判断される可能性が高いです。 入居予定のビルや周辺にそのような店舗がないか確認しておきましょう。3-4. 公正な事業運営のための要件
これは派遣事業を公正に持続していくための要件です。 登録手数料として金銭を要求したり、業務に関係のないサービスへの登録を義務付けたりすると、この要件を満たしていないとみなされます。 厚生労働省の認可基準では、以下のような文言で公正な事業運営を行うための要件を定めています。・労働者派遣事業を当該事業以外の手段(会員の獲得、組織の拡大、宣伝等)として利用しないこと ・登録時に手数料に相当するものを徴収しないこと
3-5. 個人情報の管理面での要件
情報が非常に大きな意味をもつ現代では、個人情報を適切に管理するのはマストだといえます。 もちろん、派遣事業においても例外ではありません。 具体的には下記のような要件を満たし、「個人情報適正管理規定」を作成しなければ厚生労働省からの認可を受けることはできません。・派遣労働者の秘密となる個人情報が業務の目的上必要になった場合、その情報を正当な範囲において正確かつ最新の状態で保つこと ・個人情報の紛失や破壊、改ざんが起こらないよう対策を講じること ・個人情報へのアクセスは社内の権限を持った人にのみ行わせ、それ以外の人のアクセスを防止するシステムを導入すること ・派遣労働者からの求めがあった場合や個人情報を保管しておく必要がなくなった場合、個人情報を破棄したり削除したりできるよう備えること
またこれらの内容を派遣従業員の求めに応じて開示する必要があります。 詳細については厚生労働省が発行している要件を参照してください。 ・お役立ちセミナー・資料ダウンロード 【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】 【キャリアアップ教育プランサンプル無料ダウンロード】4. 認可取得までの流れと必要書類
 派遣事業で起業するにあたって満たさなければならない要件を、厚生労働省の認可基準に照らして説明してきました。
ここからはそうした認可のステップや、その際に必要な書類のリストをご紹介します。
できるだけ確実に認可を得るためにできることは事前準備に尽きます。
特に書類不備で不許可にならぬよう、書類作成には気を配らなければなりません。
派遣事業で起業するにあたって満たさなければならない要件を、厚生労働省の認可基準に照らして説明してきました。
ここからはそうした認可のステップや、その際に必要な書類のリストをご紹介します。
できるだけ確実に認可を得るためにできることは事前準備に尽きます。
特に書類不備で不許可にならぬよう、書類作成には気を配らなければなりません。
4-1. 派遣会社を設立するまでの大まかな流れ
先に触れた「労働者派遣事業許可」を得るためには、「派遣元責任者講習」を受講した派遣元責任者を最低1名置かなければなりません。 また、厚生労働省による審査を受ける前に労働局からの調査が入ることになります。 申請から認可取得まで最短で2ヶ月ほどを要するため、起業をするタイミングや時期を見据えてスケジューリングしておきましょう。1:派遣元責任者講習を受ける
厚生労働省のサイトに掲載されている講習受講機関で、派遣元責任者講習を受講しましょう。 講習は朝から夕方まで1日で行われます。 この講習を受け、なおかつ要件を満たしている者のみが派遣元責任者として業務に従事できるようになります。2:必要書類の作成と提出
必要な書類を揃え、記入や捺印の上提出します。 まず、最も大切な書類が下記3種類の申請書および計画書です。・労働者派遣事業許可申請書(様式第1号):3部(正本1通、写し2通) ・労働者派遣事業計画書(様式第3号):3部(正本1通、写し2通) (複数事業所を同時に申請する場合、事業所ごとに作成) ・キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2):2部(正本1通、写し1通)
加えて、上記の書類に添付しなければならない書類が18種類あります。 入手や作成自体は難しくありませんが、必要な書類が揃っていなければ不備とみなされるので繰り返しチェックしておきましょう。・定款または寄付行為 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・役員の住民票 ・役員の履歴書 ・派遣元責任者の住民票 ※役員が兼務する場合は不要 ・派遣元責任者の履歴書 ※役員が兼務する場合は不要 ・派遣元責任者講習の受講証明書 ※許可申請日前3年以内に受講したもの ・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 ※会社設立後最初の決算期を終了していない法人は会社成立時の貸借対照表のみ ・最近の事業年度における法人税の納税申告書 ※会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は不要 ・最近の事業年度における法人税の納税証明書 ※会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は不要 ・事業所施設に関する書類 ※建物の登記事項証明書または建物の賃貸借契約書 ・個人情報適正管理規程 ・自己チェックシート(様式第15号) ・就業規則又は労働契約の該当箇所(写し) ・就業規則(労働基準監督署の受理印があるページの写し) ・派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し ・キャリアアップに資する教育訓練(整理用シート) ・企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
書類に関する不明点がある場合には、労働局で相談に乗ってもらえる場合もあります。 お近くの労働局に窓口がある場合、書類提出前に相談しておくと安心です。 (参考:神奈川労働局)3:労働局による調査
労働局では主に書類の不備や申請内容に関するチェックを行います。 また、この段階で担当者による現地調査が実施されます。 労働局からの電話に出られなかったことで不審がられることもあるので、この時期は常に電話に出られるよう特に気を配っておく必要もあります。4:厚生労働省による審査・認可の通達
労働局による調査後に、厚生労働省の審査が始まります。 審査の内容は労働局で行われるものとさほど変わりませんが、気を抜くことのないようにしましょう。 厚生労働省による審査後に労働政策審議会の意見聴取が行われ、最終的な可否が決定されます。 申請が認められても認められなくても通達はされるので、その内容で結果を知ることとなります。 ・お役立ちセミナー・資料ダウンロード 【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】 【キャリアアップ教育プランサンプル無料ダウンロード】5. 書類作成時のポイント
最後に、特にご相談の多い2つの書類について、記入時のポイントを簡単にご説明します。5-1. 労働者派遣事業計画書
労働者派遣事業許可を受ける際にはこの「労働者派遣事業計画書」が必要になります。 これは簡単に言えば派遣会社を適切に運営し、そこで働く人の労働環境や待遇を良く保つための計画書です。 この書類を作成する上で最も大切なことは「公正に事業を行い、従業員の環境をより良くするための」計画を立てることです。 ひとつひとつの細かい記入事項はありますが、どれも派遣事業者を適正な道に導くためのもの。そうした本質的な部分を見据えて書類を作成するのが大切です。 そして許可を得ることができた後も、毎年6月末までに「労働者派遣事業報告書」の提出が義務付けられています。 計画と実行、そして次の計画の立案までを1年のサイクルで行わなければならないのです。 こちらは「労働者派遣事業報告書」を作成する際のポイントをまとめた記事ですが、根本の部分は「労働者派遣事業計画書」と同じです。 ぜひより詳しいポイントを知りたい方は参考にしてみてください。5-2. キャリア形成支援制度に関する計画書
こちらは派遣会社で従業員として働く人のキャリア形成を促進するための計画書です。 計画書では実際のカリキュラムの内容を記入することになるので、自社で行うキャリアアップ訓練の内容を把握し、嘘偽り無く記入することが求められます。 「派遣の学校」では充実した教育訓練プログラムを用意しており、もちろん「キャリアアップ形成支援制度に関する計画書」に対応したカリキュラムも多数ご用意しております。 キャリアアップ教育訓練についての無料セミナーも開催しております。ぜひご参加ください。 【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】6. 万全な事前準備でスムーズな開業を
 起業に必要な資格や手順はシンプルではありますが、それに伴う作業にはかなりの労力や時間を割くことになります。
手続きや審査の際に慌てないようにするためにも、スムーズに開業するためにも事前準備は十分すぎるほどしておきましょう。
キャリアアップ訓練のカリキュラムに迷ったら「派遣の学校」にご相談を。
各業種や従業員の方の属性を鑑み、最適なカリキュラムを提案いたします。
起業に必要な資格や手順はシンプルではありますが、それに伴う作業にはかなりの労力や時間を割くことになります。
手続きや審査の際に慌てないようにするためにも、スムーズに開業するためにも事前準備は十分すぎるほどしておきましょう。
キャリアアップ訓練のカリキュラムに迷ったら「派遣の学校」にご相談を。
各業種や従業員の方の属性を鑑み、最適なカリキュラムを提案いたします。
7. 申請準備が楽になる無料オンラインセミナー開催中
申請準備の手間を少しでも減らしていただくために、派遣の学校では、各種無料セミナーを実施しています。 これまでの派遣会社様へのご支援実績をもとに、分かりにくい派遣法の解釈や提出に必要な書類の作成方法を事例を交えながらお伝えします。 無料で実施していますので是非お気軽にご参加ください。 【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】8. 「キャリアアップに資する教育訓練」の資料
8-1. PDFダウンロード
2022年3月末まで延長を岸田総理大臣が表明した雇用調整助成金コロナ特例措置について
※追記2022年5月31日に雇用調整助成金特例措置の令和4年(2022年)7月~9月末まで継続の方針が発表されました。 政府方針として令和4年(2022年)7月~9月は雇用調整助成金特例措置を継続し、地域特例・業況特例が設けられています。 9月以降については8月末に発表されるとのことです。 ▼詳細は厚労省ページをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html ※追記2022年2月25日に雇用調整助成金特例措置の令和4年(2022年)4月~6月末まで継続の方針が発表されました。 政府方針として令和4年(2022年)4月~6月は雇用調整助成金特例措置を継続し、地域特例・業況特例が設けられています。 7月以降については5月末に発表されるとのことです。 ※11月24日に雇用調整助成金特例措置の令和4年(2022年)4月以降について、予定として発表がありました。 2022年4月以降の予定はあくまでも予定で、コロナの状況を見ながら2022年2月中に正式発表を行うとのことです。 雇用調整助成金特例措置については、上限金額を縮減して継続の予定です。 地域※1・業況※2の特例に該当する企業は現状と同じく90%~100%、上限金額15,000円での対応が2022年3月末までは変わらず継続となります。 それ以外の企業は、80%~90%、上限金額13,500円の対応、そして2022年1月2月は上限金額が11,000円、3月は9,000円に縮減となります。 ※1:緊急事態宣言が出ていた地域 ※2:令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。 令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。 詳しくは厚生労働省発表のリーフレットを参照してください。 令和3年11月24日 リーフレット 令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 10月14日に岸田総理大臣が雇用調整助成金の特例について、来年3月までの延長を発表しました。 そして10月19日の厚生労働省サイトでも正式に発表されました。 厚生労働省サイト:報道発表資料 > 2021年10月 > 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 選挙を見越した発表ではありますが、厚労省サイトでも発表されたため間違いなく実施されるものと考えられます。 今回の発表のポイントは下記の3つです。 1.現状の助成内容と同じ措置が令和3年12月末まで継続する。 2.雇用調整助成金特例措置は令和4年3月末まで継続する。 3.12月以降の助成内容については11月中に発表する。 現状の助成内容とは、2021年5月から適用された内容となります。 詳しくは下記厚労省ページの「5月以降の対応内容」をご参照ください。 厚生労働省サイト:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) コロナ禍が落ち着きを見せてはきていますが、まだまだ事業者様には厳しい状況かと存じます。 雇用調整助成金特例措置に対応した休業者教育訓練eラーニングをご検討いただければと思います。
優良派遣事業者認定制度とは?認定基準をわかりやすく解説します!
 慢性的な人手不足により、派遣会社の需要は増加しており、派遣事業を新しく始める企業もたくさんあります。
そして、その中でも「選ばれる」派遣会社になりたいという思いは、どの会社の方も持っているはずです。
この記事では、良い派遣会社を測る大事な指標のひとつである「優良派遣事業者認定制度」にフォーカスします。
この制度がどのようなものなのか、また認定されるためのポイントはどこにあるのかを解説していきます。
そして認定項目の一つである「教育」に関して特に力を入れている企業が近年増えていることを踏まえ、教育に関するお話も重点的にご説明します。
慢性的な人手不足により、派遣会社の需要は増加しており、派遣事業を新しく始める企業もたくさんあります。
そして、その中でも「選ばれる」派遣会社になりたいという思いは、どの会社の方も持っているはずです。
この記事では、良い派遣会社を測る大事な指標のひとつである「優良派遣事業者認定制度」にフォーカスします。
この制度がどのようなものなのか、また認定されるためのポイントはどこにあるのかを解説していきます。
そして認定項目の一つである「教育」に関して特に力を入れている企業が近年増えていることを踏まえ、教育に関するお話も重点的にご説明します。
目次
1. 優良派遣事業者認定制度とは
そもそもこの制度がどのようなものなのか説明できる方はそう多くはないはずです。 字面を見ていると「優良な」派遣会社に対して認定が行われるのは分かりますが、どのような派遣会社が良いと判断されるのでしょうか。 一つずつ解説していきます。1-1. 三者にとって良い環境をつくるための制度
優良派遣事業者認定制度は、簡単に言えば「三者にとって良い環境をつくるための制度」です。 ここでいう三者とは派遣労働者、派遣元事業者、派遣先事業者のことです。 それぞれがメリットを享受することのできる健全な事業ができるような仕組みを作るため、この制度が生まれました。1-2. 認定基準は厚生労働省が公開
認定基準は厚生労働省の公式サイトで公開されています。 「社内監査体制に関する基準」や「派遣社員のキャリア形成に関する基準」など項目別の認定基準が設定されています。また、サイト上では基準に達しているか確認するためのチェックリストも見ることができます。 リストはPDF形式でダウンロードすることもできるので、ぜひ一度目を通してみてください。 きっとこの制度の趣旨と今後すべきことが分かるはずです。2. 優良派遣事業者に認定されることのメリット
ここまでで制度の概要を掴んでいただけましたでしょうか? それでは、認定を受けることによって得られるメリットをご紹介します。 もちろん認定自体は経営していく上で必須なものではないので、取得しないという選択肢もあります。 しかし、今後事業を存続・拡大していくためには認定を取得することを強くおすすめします。 派遣事業者・派遣社員・派遣先事業者それぞれの立場で享受できるメリットはたくさんありますが、中でも大きなメリットを3つ挙げます。2-1. メリット①派遣先企業や従業員の企業選びの指標になる
優良派遣事業者として認定されると、認定の効力が続く間は「認定マーク」を使用できるようになります。 派遣社員の受け入れを考えている企業や、派遣社員として働こうと思っている人たちにとって、このマークは企業を選ぶ際の判断材料のひとつになります。 優良派遣事業者認定されている企業の中から一緒に仕事をする相手を選びたいと考えている人も多くいます。 認定を受けることで、そうした人たちの目に留まるようになります。2-2. メリット②派遣元企業は信頼を得やすくなる
優良派遣事業者の認定は厚生労働省が行います。 そのため、認定を受けると健全な事業を行っていることが対外的に保証されることになります。 これは株式上場する際や銀行の融資を受ける際などに良い影響を及ぼすことがあります。2-3. メリット③適切な環境整備がなされる
これは根本的な話なのですが、基準を満たすことができるように社内環境の改善を行うと 派遣社員や派遣先企業、そして自社にとって最適な環境を作ることにそのまま繋がります。 事業を営んでいく上でよりよいサイクルが生まれるのは必至なので、むしろ認定を得ること自体よりも大切であるといえます。3. 申請に必要な必須条件
上記ご紹介したように認定されることでメリットを得ることはできるのですが、派遣会社であればどの企業でも申請できるわけではありません。 厚生労働省が定める要件を満たす必要があります。 事前に要件を確認し、「こんなはずじゃなかった」とならないようにしましょう。3-1. 9つの要件とは?
要件は全部で9つあり、申請を行う際には全てを満たしている必要があります。 要件は次のとおりです(要約している箇所があります)。
一見、9つと聞くと条件がとても多いように聞こえますが、そのひとつひとつを噛み砕いてみると、決してハードルが高いわけではないのが分かります。 法令や社会的通念に従って通常業務をしっかり行っていれば、そこまで意識せずとも申請資格を得ることはできるはずです。- 申請時に、事業主が労働者派遣事業の許可を受けていること。
- 直近5年間で労働関係法令(労働基準法・職業安定法など)に関する重大な違反をしていないこと。
- 労働者派遣事業の許可・届出後、3年以上の事業実績があること。
- 直近過去3年間、税金を滞納したことがないこと。
- 直近過去3年間、派遣労働者への給与の支払い遅れがなかったこと。
- 直近過去3年間、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
- 直近過去3年間、厚生労働省から「労働者派遣事業改善命令」や「労働者派遣事業停止命令」を受けていないこと。 また3年以上前にこうした命令を受けた場合でも、申請時にはすでに命令を解除されていること。
- 認定日のある月の前月から遡る12か月間で、違法な法定時間外労働及び休日労働がないこと。
- その他、この制度の趣旨に反する事実がないこと。
3-2. 新規事業者は3年の基準に抵触しないように注意
ただ、注意点もあります。 問題なく業務を行っていても、新しい企業の場合には3.の事業実績の項目に触れる可能性があります。 少なくとも3年間は事業実績を積み重ねてから申請を行うようにしましょう。 もちろんその間に認定に向けた準備をすることはできますので、3年経過した時点で申請をスムーズに行うことができるように備えておくと良いでしょう。4. どんな認定基準がある?キャリア教育はどうしたら良い?
要件を満たすことができたら、ようやくスタートラインに立つことができます。 冒頭で認定基準に関して少しだけ触れましたが、ここでは具体的な内容をご紹介します。 そして特に従業員に対するキャリア教育はどのようにしたら良いか、重点を置いてご説明します。4-1. 4つに大別される認定基準
優良派遣事業者として認定されるためには、大きく分けて下記の4つのジャンルの認定基準を満たす必要があります。
ひとつひとつの認定基準に関してより詳しい解説を行っていきます。- 事業が健全に行われているか (事業体に関する基準)
- 派遣社員の適正就労が行われているか (派遣社員の適正就労とフォローアップに関する基準)
- 派遣社員への教育や処遇が充実しているか (派遣社員のキャリア形成と処遇向上の取り組みに関する基準)
- 派遣先企業に関する環境整備を行っているか (派遣先へのサービス提供に関する基準)
4-2. 事業が健全に行われているか
これは「事業体に関する基準」に当たるもので、主に社内の環境に関する指標が定められています。 安定した財務状況で経営が行われているか、社内監査体制が整っているか、といった経営上の基本事項に加え、内勤の社員への教育も基準に含まれています。 またプライバシーポリシーを有し、それに沿って個人情報の管理をしっかりと行っているかという項目もあります。 たくさんの個人情報を知り得る派遣事業者の立場だからこそ、こうした個人情報に関する事柄には人一倍気を配らなければなりません。4-3. 派遣社員の適正就労がされているか
これは「派遣社員の適正就労とフォローアップに関する基準」にあたるものです。 チェックは派遣社員を採用する段階から始まります。 適正な内容で募集を行い、応募者には明確な説明を行わなければなりません。 そして入社後にも必要な情報は正確に、包み隠さず派遣社員に伝える必要があります。 ここには必要な情報を求められたら開示することも含まれます。 また派遣社員からの意見や不満をしっかりと拾い上げ、それを適切な場所に伝えてより良い環境づくりをしなければなりません。 保険への加入やメンタル面でのサポート、ワークライフバランスへの配慮など派遣社員ひとりひとりがより良い仕事ができるように努めることで、認定の可否に関わらず優良な事業者に近づくことができるといえるでしょう。4-4. 派遣社員のキャリア形成に関する仕組みや取り組みが充実しているか
そして今回重点を置いてご紹介する基準がこちら。 厚生労働省の文言でいうと「派遣社員のキャリア形成と処遇向上の取り組みに関する基準」にあたるものです。 この項目はその名の通り派遣社員をただ就労させるだけでなく、しっかりとこの先のキャリアまで見据えて管理をしているか測るためのものです。 派遣社員本人の働きに対して適正な評価を下し、フィードバックをすることで成長の糧にすることができますし、キャリア形成に配慮した仕事の配分を行うことで本人のモチベーションにもつながります。 もちろん認定を目指す上で必要な事項ではあるのですが、本当に派遣社員のことを考えていれば自然に行われるであろうことばかりです。 そしてキャリア教育についての言及もあります。 厚生労働省の文言を引用すると、「派遣社員に対して教育訓練の機会提供や支援を行っていること」が基準となっているそうです。 このキャリア教育に関して、どのような教育をどの程度行えばよいか分からず悩まれている企業が多くいらっしゃいます。 ぜひ一度e-Learningで派遣社員のキャリア形成をサポートする「派遣の学校」の導入もご検討ください。 また、こうしたキャリア教育に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。4-5. 派遣先企業に関する環境整備を行っているか
こちらは「派遣先へのサービス提供に関する基準」にあたる内容です。 派遣会社は人員が必要な企業に対して社員を派遣しますが、その派遣先で業務を行う上での必要事項を基準としてまとめたものとなっています。 派遣先企業のニーズを汲み取った上でスムーズな仕事ができるような仕組みの構築や取り組みの実施が求められます。 社会的規範に加えて派遣先のルールやマナーが存在することもあるので、そうした部分に対応するための適切な教育も必要とされています。5. 申請から認定までのスケジュール
優良派遣事業者として認定されるまでのスケジュール感を把握していただくため、過去の認定スケジュールをもとに流れをご説明します。 申請してからすぐに認定がもらえるわけではないので、優良派遣事業者認定に向けた申請を行う際にはスケジュールに余裕を持つ必要があります。5-1. 大まかな流れ
申請から認定までの大まかな流れは下記の通りです。
まずは全国で開かれる説明会に参加し、必要な書類を揃えて申請を行います。 その上で審査に必要な事前エビデンスを審査日までに提出し、現地もしくはオンライン上での審査を受けます。 そしてその後審査が行われると、認定事業者の公表により認定されたかどうかが分かります。- 説明会への参加
- 申請
- 審査(現地・オンライン)
- 認定事業者の公表
5-2. 前期審査と後期審査の期間
認定審査は1年に前期と後期の2回行われます。 申請の受付期間はそれぞれ決まっているため、もし申請が間に合わなかった場合には次期の申し込み期間まで待たなければなりません。 例年申請の受付は前期で7月上旬〜下旬まで、後期で11月中旬〜下旬となっています。 そして最終的な認定公表は前期で9月30日、後期で3月31日です。 申請から認定までの期間は前期で約2ヶ月、後期で約4ヶ月であることを考えると、前期日程の方が審査期間が短いことになります。 ただ、実際には申請を行う前に説明会に参加する必要があるため、そのスケジュールも確保しておかなければなりません。5-3. 認定されるまでのスケジュール
ここからは2021年度後期の認定審査スケジュールをもとに、申請から最終的に認定を得るまでに必要な期間をより詳しくご紹介します。 2021年度後期のスケジュールは下記の通りです。
説明会への参加から見ると最大7ヶ月以上かかることになります。 そのため申請後「すぐ」認定とはいえないでしょう。 まずは説明会へ参加し、早めに準備を進めておくことをおすすめします。 厚生労働省のホームページからは最新の日程が公表されているので、申請を考えている日程のスケジュールを事前に確認しておきましょう!- 8月24日〜9月21日 全国説明会
- 10月21日〜11月12日 後期申請受付
- 申請受付後〜1月末まで 審査期間(訪問・オンライン)
- 3月31日(予定) 後期認定企業公表
6. 押さえておくべきポイント
 この記事でご紹介した内容から、優良派遣事業者として認定を受けるために押さえておくべきポイントを3つにまとめました。
どれも大切なことなので、申請を行う際にはぜひ心がけてみてください。
この記事でご紹介した内容から、優良派遣事業者として認定を受けるために押さえておくべきポイントを3つにまとめました。
どれも大切なことなので、申請を行う際にはぜひ心がけてみてください。
6-1. 事前に情報収集をしておく
制度の概要や認定基準、申請要件などの情報は厚生労働省の公式サイトですべて公開されています。 認定基準については項目ごとの内容が端的にまとめられたチェックリストを閲覧することができるので、審査前に自社の状況をセルフチェックできるようになっています。 申請のスケジュールは少し長めなので、認定されず再度申請を行うとなるとかなりの時間がかかってしまいます。 事前の準備を怠らないようにして確実に認定を得られるようにしましょう。6-2. スケジュール管理をしっかりと
事前の準備に通じる部分もありますが、申請を行う上でスケジュール管理は必須ともいえます。 申請後には、訪問もしくはオンラインでの審査の前に、実績や事例、管理状況を示すエビデンスを提出する必要があります。 この際に必要となる書類は複数になることも多いため、エビデンスを準備するための期間も考慮してスケジュールを組みましょう。 最新の認定審査のスケジュールは公式サイトで確認できます。6-3. 認定のためではなくより良い環境のために
この認定制度の趣旨を鑑みると、厚生労働省は優良派遣事業者の認定を行うことで一定の基準をクリアした「優良な」事業者を増やし、識別できるようにしようとしていることが分かります。 そのため認定だけを狙って一時的な対策をするのはおすすめできません。 認定基準には従業員のために、派遣先企業のために、そして自分たちの企業のために必要なことが明確に示されています。 長い目で見れば、認定を取得することで認定の取得以外のメリットもたくさん享受できることでしょう。7. 従業員や企業のために制度認定を目指しましょう
 優良派遣事業者に認定されることはもちろんたくさんのメリットをもたらしますが、ただ認定だけを目的にするべきではありません。
従業員や会社のことを本当によく考え、少しでも良い環境を作ろうと努めなければならないのです。
よい環境づくりの先に、制度認定という副産物があるようなイメージです。
そして晴れて優良事業者として認定を受けた後も、それで終わりではありません。
その良い環境を保ち、従業員や会社が成長を続けられるように臨機応変に派遣会社としてのあり方を変えていかなければなりません。
ぜひ制度認定をきっかけにご自身の会社のことを見つめ直してみてください。
「派遣の学校」では派遣社員の方の成長やキャリアアップを主眼に置いたコンテンツを多数ご用意しています。
派遣社員の方の教育に関するお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
優良派遣事業者に認定されることはもちろんたくさんのメリットをもたらしますが、ただ認定だけを目的にするべきではありません。
従業員や会社のことを本当によく考え、少しでも良い環境を作ろうと努めなければならないのです。
よい環境づくりの先に、制度認定という副産物があるようなイメージです。
そして晴れて優良事業者として認定を受けた後も、それで終わりではありません。
その良い環境を保ち、従業員や会社が成長を続けられるように臨機応変に派遣会社としてのあり方を変えていかなければなりません。
ぜひ制度認定をきっかけにご自身の会社のことを見つめ直してみてください。
「派遣の学校」では派遣社員の方の成長やキャリアアップを主眼に置いたコンテンツを多数ご用意しています。
派遣社員の方の教育に関するお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
8. 派遣許可申請準備が楽になる無料オンラインセミナー開催中
派遣許可申請準備の手間を少しでも減らしていただくために、派遣の学校では、各種無料セミナーを実施しています。 これまでの派遣会社様へのご支援実績をもとに、分かりにくい派遣法の解釈や提出に必要な書類の作成方法を事例を交えながらお伝えします。 無料で実施していますので是非お気軽にご参加ください。 【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】
コールセンター・店舗販売派遣の専門的なキャリアアップ教育訓練ご用意しました
今回、株式会社プロシーズでは株式会社JBMコンサルタントと提携して「コールセンター」・「店舗販売」派遣社員へのキャリアアップ研修の専門教材の利用を開始しました。 改正派遣法に特化したプロシーズの【派遣の学校eラーニングシステム】とOffice・IT系、マネジメント系、ヒューマンスキル系教材に加え、JBMコンサルタントが開発した「コールセンター」「店舗販売」の各分野で求められる専門知識が学べる教材を【全180講座約332時間分】搭載し、派遣元企業様のキャリアアップ教育訓練にご利用いただけます。 追加されたコールセンター・店舗販売向けの教材はこちらです。 ■〈プログラム例 : コールセンター〉 オペレーター向け - 役割と心構え - 電話でのクレーム対応 - コミュニケーション理論と実践 - 顧客心理を読み取った対応文作成 - 電話によるセールス勧奨 SV・リーダー以上 - SV/リーダーとしての心構えと役割・スキル - 論理的思考 - 人材育成の手法 - 指標管理の重要性と読み方 - モニタリング/フィードバックの効果と手法 ■〈プログラム例 : 店舗販売〉 販売スタッフ向け - 職場のマナーと守るべきルール - 販売スタッフの役割と心構え - 接客用語とビジネス用語の使い方 - 購買心理と応対の流れ - 製品の提示・説明・クロージング リーダー以上 - 業務改善におけるPDCAサイクル - 来客や電話でのクレーム対応 - 顧客満足 - 会話の基本テクニック - サービスの特性 コールセンター・店舗販売派遣の専門的なキャリアアップ教育訓練をお探しのご担当者様、ぜひ一度ご検討ください。 ▼コールセンター・店舗販売の専門教材ラインナップ https://www.pro-seeds.com/haken/course/callcenter-sales/ 資料請求・デモ希望などお問い合わせはこちら: https://www.pro-seeds.com/haken/contact/claim/?utm_source=blog20210531
雇用調整助成金特例措置、2022年3月末までの延長の方針表明
※追記2022年5月31日に雇用調整助成金特例措置の令和4年(2022年)7月~9月末まで継続の方針が発表されました。 政府方針として令和4年(2022年)7月~9月は雇用調整助成金特例措置を継続し、地域特例・業況特例が設けられています。 9月以降については8月末に発表されるとのことです。 ▼詳細は厚労省ページをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html ※2021年10月20日追記 雇用調整助成金の特例措置について、来年の令和4年3月末まで延長が発表されました。 現在と同じ助成内容については令和3年12月末までの延長ということで、 助成内容の変更はありつつも、雇用調整助成金特例措置は令和4年3月末までは継続されます。 ぜひ休業者教育訓練eラーニングをご検討いただければと思います。
雇用調整助成金特例措置、2021年6月30日まで延長正式発表がありました。 現状5月6月については90%助成で縮減しつつ継続予定というところまでの方針は出ていましたが、つい先ほど、厚労省ホームページで継続決定の発表がありました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 変更点は、こちら。 ・上限が1日15,000円から13,500円になること。 ・補償が10/10(100%)から9/10(90%)になること。 ただし、3ヶ月間で売り上げが30%以上落ちている企業、まん延防止対策地域で時短要請に応じている飲食店は今まで通り100%の補償が続くということです。 そして、教育を行った場合の教育訓練加算(1日2,400円、半日1,200円)についてはそのまま継続とのことです。 雇用調整助成金特例措置の6月末延長に伴い、弊社休業者教育訓練eラーニングコースサービスも6月末まで同条件でご利用いただけます。 緊急事態宣言が延長されて苦しい状態が続いております。 こんな時こそ教育訓練を行って社内の地力を上げていただければと思います。 休業者教育訓練eラーニングコースも特例措置継続に沿ってご利用いただけますので、ぜひご検討ください。
労働者派遣事業の令和2年6月1日現在の状況が発表されました
厚生労働省から「労働者派遣事業報告書」(令和2年6月1日現在の状況報告)の集計結果が発表されました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079194.html 内容はこちらです。【労働者派遣事業令和2年6月1日現在の状況概要】
1 派遣労働者数・・・・・・・・・・・・約156万人(対前年比:0.2%減) (1)無期雇用派遣労働者 610,683人(対前年比:10.9%増) うち協定対象派遣労働者* 554,570人(対前年比: - ) (2)有期雇用派遣労働者 951,407人(対前年比:6.3%減) うち協定対象派遣労働者* 859,780人(対前年比: - ) 2 製造業務に従事した派遣労働者数・・・約31万人(対前年比: 4.4%減) (1)無期雇用派遣労働者 115,730人(対前年比: 19.1%増) うち協定対象派遣労働者* 109,682人(対前年比: - ) (2)有期雇用派遣労働者 195,930人(対前年比: 14.4%減) うち協定対象派遣労働者* 183,494人(対前年比: - ) *労働者派遣法第30条の4第1項の協定(労使協定方式)対象である派遣労働者の数 予想されておりました通り、2020年4月1日同一労働同一賃金が適用され派遣先均衡均等法式と労使協定方式を選ぶにあたって、90~94%が労使協定方式が選ばれる結果となっています。 労使協定方式の場合、正規社員との待遇差に明確な説明が必要になってきます。 こちらの記事などもご参照いただければと思います。
雇用調整助成金特例措置で、一部大企業も助成率が100%に引き上げされました
雇用調整助成金の特例措置において、大企業の助成率は解雇無しで4/5が最大でしたが、緊急事態宣言に伴い、 一部大企業でも助成率が10/10,100%に引き上げになりました。 2月の段階で注意書きとして書かれていた下記の内容が確定した形になります。 緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げます。 緊急事態宣言で時短営業や制限をきちんと守った大企業と、30%以上の落ち込みがあった大企業が対象となります。 また、現状特例措置が申請できる都道府県は緊急事態宣言が発布されているところとなります。 ちなみに3月9日現在の大企業が対象となる特例措置期間は下記の通りです。 ========================= ●埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県: 令和3年1月8日~3月21日 →4月30日までの休業が特例対象 ●岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県: 令和3年1月14日~2月28日 →3月31日までの休業が特例対象 ●栃木県: 令和3年1月14日~2月7日 →3月31日までの休業が特例対象 ========================= 中小企業は、一律4月末までが特例措置対象期間となります。 大企業と中小企業の区分けは、下記の中小企業の定義に当てはまらない企業は大企業となります。 ========================= ◆中小企業の定義 どちらかに当てはまるのが中小企業 ①資本金の額または出資金の総額 小売業:5,000万円以下 サービス業:5,000万円以下 卸売業:1億円以下 それ以外:3億円以下 ②常時使用する労働者数 小売業:50人以下 サービス業:100人以下 卸売業:100人以下 それ以外:300人以下 ※個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することになります。 ========================= 詳細は厚労省ページの 【雇用調整助成金FAQ(令和3年3月5日現在版)】 (09)緊急事態宣言等対応特例をご確認ください。 休業者教育訓練eラーニングコースも特例措置継続に沿ってご利用いただけますので、ぜひご検討ください。
雇用調整助成金特例措置、2021年4月30日まで延長正式発表
雇用調整助成金で、eラーニング利用可能、中小企業なら100%費用が返ってくる特例措置について、2021年4月30日まで延長が正式に発表されております。 厚労省サイト:雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 既に2月末の段階でも、『緊急事態宣言が全国で開けた翌月まで』という延長期間についての決定は出ていたのですが、 やっと4月30日までという日程が発表されました。 また、社員だけではなく、パートやアルバイトの方、つまり雇用保険の被保険者でない従業員への休業手当の助成は、緊急雇用安定助成金として助成が可能です。 詳しくは厚労省ページご参照ください。 厚労省サイト 休業者教育訓練eラーニングコースも特例措置継続に沿ってご利用いただけますので、ぜひご検討ください。