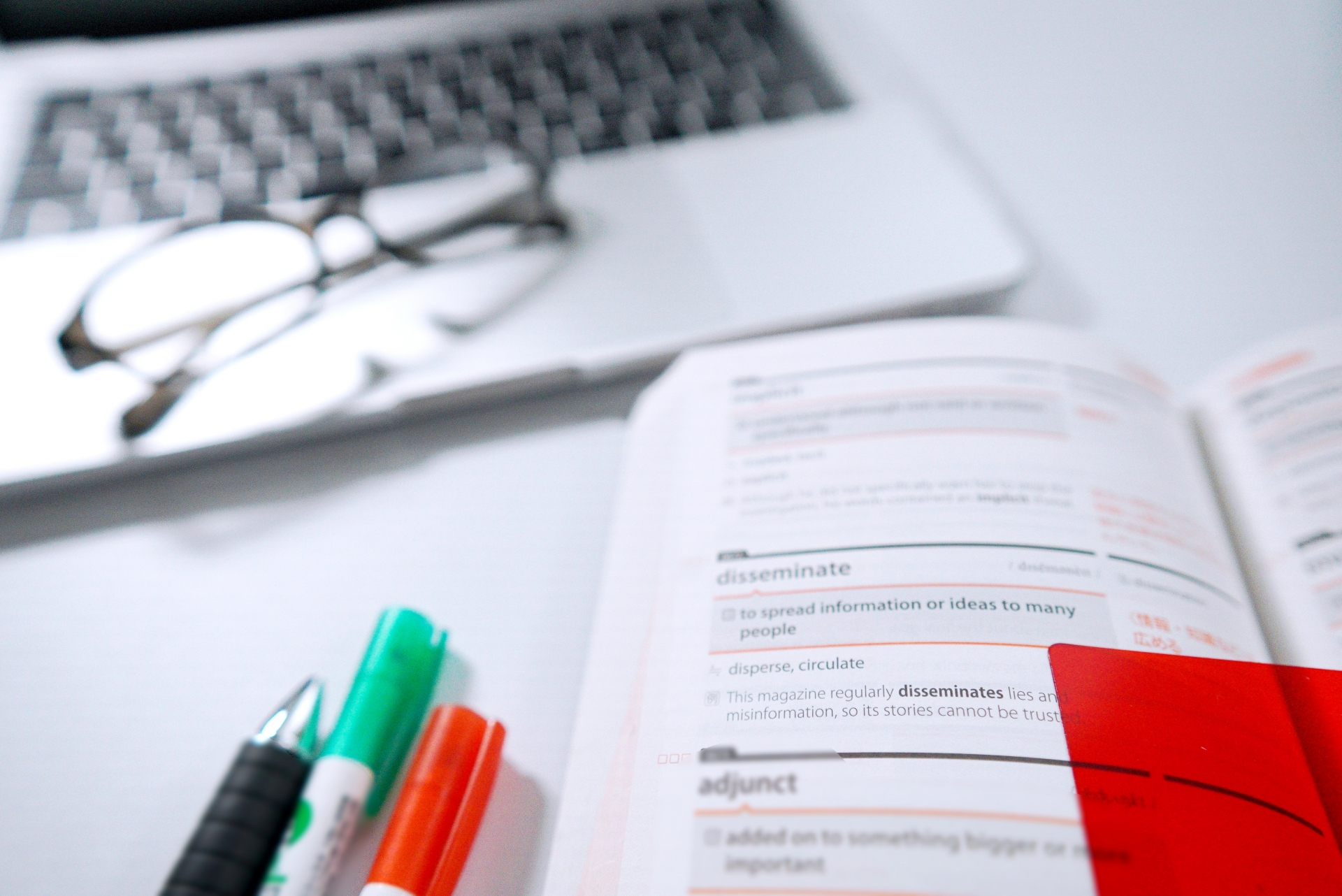
目次
- 紙の試験から、オンライン試験へ
- オンライン試験システムとは?
- システム導入のメリット
- 選び方|チェックポイント解説
- オンライン試験システムおすすめ10選【2025年版】
- 実際の導入効果|研修会社・団体での活用例
- 導入の流れ|失敗しないためのステップ
- まとめ
紙の試験から、オンライン試験へ
近年、試験のオンライン化が急速に進んでいます。
文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調査」では、2025年度からCBT形式での実施が段階的に予定されており、小中学校においてもオンライン試験の導入が進みつつあります※。
研修会社や資格試験を運営する団体では、全国からの受験が可能になり、紙の試験運用にかかっていた人件費や郵送コストを削減できることから、オンライン試験システムの導入が急増しています。
※:令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査)のCBTでの実施について
企業の昇格試験、資格団体の認定試験、学校の入学試験や選抜試験など、「公平性」や「厳格性」が求められる場面でも、オンライン試験は従来の紙試験に引けを取らない品質に進化してきました。
しかし、システムの機能や使い勝手、コストはサービスによって大きく異なります。
そこで本記事では、オンライン試験システムの選び方や導入の流れ、おすすめのサービス10選を、比較表つきでわかりやすくご紹介します。
オンライン試験システムとは?
オンライン試験システムとは、インターネット上で試験の作成・配信・採点・結果公開までを一括で管理できる仕組みのことです。
従来、紙と人手に頼っていたプロセスが、すべてデジタル化・自動化されるため、運営側にとっても受験者にとっても大きなメリットがあります。
主な機能は次のとおりです。
- 試験問題作成:選択式、記述式、〇×式など多様な形式に対応
- 受験管理:受験者データの管理、受験日時の指定、グループ分けなど
- 自動採点・結果公開:解答は自動で採点され、合否結果を即時で受験者に公開
- 結果集計:全受験者の解答・得点、平均点・偏差値などのデータを一括出力
- 不正防止対策:カメラ監視、試験画面以外の画面表示を防ぐ、ログ解析など
オンライン試験システム導入のメリット
オンライン試験システムを導入することで、試験運営における多くの課題を解決できます。以下では、代表的なメリットを紹介します。
1. 運営コストの削減
問題用紙の印刷・封入・配送・保管といった手間と費用を削減することができます。
会場の手配や試験監督者の人件費も不要となるため、運営全体のコストを大幅に抑えることが可能です。
そうすることで、小規模な試験でも採算が取りやすくなり、安定した試験運営につながります。
2. 業務の効率
解答用紙の回収や仕分け、採点業務、さらには採点結果の多重チェックといった作業も不要になります。
結果通知も自動化されるため、試験結果のフィードバックをスムーズに行うことができ、受験から結果確定までの時間を大幅に短縮できます。
さらに、受験後の集計も容易に行えるほか、記名忘れの心配もなくなることで、受験者の満足度向上にもつながります。
試験会場への出張が不要になるため、担当者の負担を減らし、通常業務に支障をきたすこともありません。
3. 受験機会の創出
オンライン試験であれば、全国どこからでも受験が可能になります。
これまで近くに試験会場がなく、受験のために宿泊や長距離移動が必要だった人でも、自宅から安心して受験できるようになります。
さらに、試験日程を複数設けやすいため受験率の向上にもつながります。
これにより、今まで受験を諦めていた人にも新たな受験機会を提供でき、結果として受験者数や受験料収入の増加も期待できます。
選び方|チェックポイント解説
1. 不正防止対策
受験者が不正をしないように監視・防止する機能がとても重要です。
たとえば、事前に顔写真や身分証をアップロードして本人確認をする「eKYC」や、試験中にカメラで顔を認証する機能があります。
さらに、試験画面以外を開けなくする「ブラウザロック」や、AIが受験者の視線や動きを検知して怪しい行動を知らせる機能、複数のカメラで受験者の周囲を確認する仕組みなどもあります。
また、問題や選択肢の順番をランダムに変えることで、答えの事前共有を防止する工夫も欠かせません。
こうした不正防止機能があるかどうかで、試験の信頼性は大きく変わります。
2. 試験の実施から採点
出題形式や採点のしやすさも重要です。
選択式や記述式だけでなく、画像や動画を使った問題、リスニング問題、ファイルを提出する問題など、目的に合った出題方法が選べると便利です。
採点については、選択式の即時採点はもちろん、記述式でもあらかじめ評価基準を設定しておくと、自動化やAIによる採点補助が可能になります。
さらに、試験日程の設定や受験リンクの配布、未受験者への自動リマインドなどの管理機能も運営の負担を減らしてくれます。
正答率や設問ごとの傾向を分析できる統計機能や、障害時にすぐに試験を再開できたり、個別対応ができる機能もあると安心です。
3. 誰でも使いやすい操作性
システムの使いやすさは、受験者だけでなく運営側の負担軽減にもつながります。
PCやタブレットのどちらからでも受験でき、専用アプリをインストールせずにブラウザだけで試験が受けられると、初めての人でも安心です。
画面の見やすさや、試験の残り時間や進行状況が分かるナビゲーション表示など、直感的に操作できるデザインも大切です。
また、文字の拡大や色の変更、画面読み上げ機能などのアクセシビリティ対応、複数言語に対応しているかなど、受験者の多様性に対応することも欠かせません。
外部ツールとの連携ができると、ポータルサイトや顧客管理システムなどに試験結果を連携でき、運営効率も高まります。
受験料をオンライン決済できる機能があれば、申込から受験までをすべてネットで一元管理ができます。
4. 同時受験人数
大規模試験の場合、同時にアクセスできる人数の上限がシステムの選定ポイントになります。
もし同時受験人数に制限があると、試験を複数の日程に分けざるを得なくなります。
その場合、公平性を保つために日程ごとに問題を変える必要があり、作問の手間が増えてしまいます。
大人数が同時にアクセスしても安定して動作するように、負荷分散設計や負荷試験がされているかは、特に資格試験や入試などの大規模運営では外せない確認項目です。
5. サポート体制と導入支援
システム自体の機能だけでなく、提供会社のサポート体制も重要な比較ポイントとなります。
受験者や運営担当者からの問い合わせに迅速に対応できる窓口があるか、試験当日にトラブルが起きた場合に専門スタッフがサポートしてくれるかといった点を確認しておくと安心です。
特に大規模試験や高頻度の試験を実施する場合は、システム障害時の対応フローやサポートの稼働時間(平日のみか、土日対応もあるか)などもチェックしておくと良いでしょう。
また、初期設定や試験の立ち上げをサポートしてくれるマニュアルや研修があるかどうかも運営負担を減らすうえで大きな要素となります。
6. セキュリティ・安全面
オンライン試験では、受験者の個人情報や試験データを扱うため、セキュリティ対策と法令遵守は欠かせません。
特に、個人情報保護法に対応しているかどうかは必ず確認しておきましょう。
加えて、情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISMS(ISO27001)や、個人情報保護の体制を示すプライバシーマークを取得している企業かどうかも、信頼性を判断する大きな基準となります。
また、受験規約を表示して同意を得る仕組みや、データの保存期間を設定できる機能があると安心です。
操作履歴・採点履歴・問題の修正履歴などのログを残せるシステムであれば、監査や社内調査、万が一のトラブル時にも根拠資料として活用できます。
加えて、システムの稼働率保証が明示されているかも重要なポイントです。
試験中にシステムが停止すると受験者・運営者双方に大きな影響を与えるため、安定稼働が保証されていることは安心材料になります。
オンライン試験システムおすすめ10選【2025年版】
ここでは、オンライン試験システムの中でも特に実績があり、幅広いニーズに対応できるサービスを10社ピックアップし、比較表つきでご紹介します。
| システム名 | 不正防止機能 | システムの使いやすさ | セキュリティ・安全 | サポート体制 |
| A社 | ◎ ブラウザロック対応 | PC/スマホ両対応、UI直感的 | ISMS取得、ログ保存対応 | 専用サポート窓口あり |
| B社 | ○ カメラ監視あり | ブラウザ受験可能 | 個人情報保護法準拠 | 平日サポート |
| C社 | ◎ AI監視機能あり | 専用ポータル連携 | Pマーク取得 | 導入支援あり |
| D社 | ○ 問題ランダム化 | UI標準的 | ISMS取得 | 大規模運営向け支援 |
| E社 | △ 監視機能限定 | シンプル操作 | ログ保存機能あり | 相談対応のみ |
| F社 | ◎ カンニング検知あり | スマホ特化UI | 個人情報保護法対応 | 受験者向けFAQ充実 |
| G社 | ◎ ブラウザロック・有人監視機能 | 多言語対応 | セキュリティ規格取得 | 土日サポート |
| H社 | ◎ AI不正検知 | ブラウザ完結 | SLA提示あり | 担当者付きサポート |
| I社 | △ 最低限の機能 | 操作は簡単 | データ暗号化 | サポート体制限定 |
| Testable | ◎ eKYC、ブラウザロック、AI監視 | シンプルUI、アクセシビリティ対応 | ISMS、Pマーク取得済 | 専任チームによる運営支援 |
実際の導入効果|研修会社・団体での活用例
資格試験団体での活用|試験のDXと公平性の確保を実現
Testableは、全国規模で認定試験を実施する多数の資格試験団体に導入されています。
たとえば、日本感染管理検定協会(JIC)様や日本認知症資産相談士協会(JDAC)様、サウナ・スパ協会様などでは、オンライン試験化によって会場設営や紙の配布・回収といった運営コストを大幅に削減。
顔認証やカメラ監視、不正防止機能(別タブ制限・ランダム出題など)を備えており、公平性の高い試験実施を実現しています。
また、合格証の自動発行や受験者データの一元管理機能により、事務局の業務負担も軽減されました。
全国の受験者に対して、安定して正確な試験運営が行える環境を整えることができています。
大規模試験にも対応できるサーバー環境を備えており、10,000人規模の同時受験も可能です。
受験途中での通信切断時も、オフラインで回答を継続できる仕組みがあり、トラブル耐性の高い設計も評価されています。
教育機関での導入
教育機関においても、Testableはその使いやすさと管理性の高さから支持されています。
同志社大学様では、学生への小テストや理解度確認テストのオンライン実施に導入され、スムーズな成績管理が可能となっています。
初心者でも扱いやすいインターフェースのため、教職員のITリテラシーに依存せず運用できるのも、大きな導入メリットです。
また、株式会社カラーズ・エデュケーション様など、専門資格講座を展開する教育機関でも、オンライン試験を提供しています。
受講者は自身のタイミングで試験に取り組めるようになり、運営側も少人数で無理なく対応可能な仕組みを構築。
さらに、今後は問題のランダム出題機能などの活用も検討されています。
導入の流れ|失敗しないためのステップ
オンライン試験システムの導入は、単にツールを選ぶだけでは成功しません。
試験の目的や受験者層、運用体制に合わせて計画的に進めることで、トラブルを防ぎ、効果的な運用につながります。
オンライン試験システムを導入する際の一般的な流れをご紹介します。
Step1|目的と要件の明確化
まずは、「どんな試験を、誰に、どのように実施したいのか」を整理することが重要です。
また、このフェーズでは必要な機能やセキュリティ要件、予算の上限なども明確にしておくと、ツール選定がスムーズに進めることができます。
- 対象
- 実施形式
- 同時受験数の規模
- 不正対策の必要性
- 合否判定や成績管理の仕組み
Step2|オンライン試験システムの比較・選定
要件に基づいて、複数のオンライン試験システムを比較します。ポイントは以下の通りです。
必要であれば、無料トライアルやデモンストレーションを依頼し、実際の操作感を確認するのがおすすめです。
- 受験者側の操作性:スマホ対応・ログインのしやすさ
- 問題形式の柔軟性:選択式・記述式・画像付き設問など
- 不正防止機能:監視・顔認証・ブラウザ制限など
- 試験中のトラブル対応:途中保存、回線切断時の復帰
- 管理画面の操作性、集計・採点の自動化
- サポート体制:導入支援・マニュアル提供など)
Step3|社内・事務局体制の整備と準備
ツールの選定後は、試験運営を担当するスタッフの役割分担やオペレーションの確認を行います。
- 試験問題の作成・入力
- 受験者への事前案内・操作説明
- 当日の問い合わせ対応(ヘルプデスクなど)
- 結果通知や証明書発行の手順
Step4|動作確認とマニュアルの配布
受験者へのマニュアル提供や事前テスト(動作確認)も重要です。
特に高齢者やITリテラシーに不安のある受験者が多い場合は、練習用テストの提供が効果的です。
- マニュアル準備・配布:操作方法やトラブル対処をわかりやすくまとめ、メールやWebで事前に受験者へ配布する
- 事前テスト(動作確認):受験環境や操作が問題なく動くか確認できる練習用テストを用意する
- サポート案内:問い合わせ先や対応時間を伝える
- フォローアップ:動作確認の完了確認やリマインドを行う
Step5|本番試験の実施
準備が整ったら、本番試験の実施です。
万が一に備えて、トラブル時の対応フローも事前に用意しておくと安心です。
たとえば、通信エラー時の再受験、途中保存データからの再開手順などが挙げられます。
- 受験者は指定された日時・URLからログイン
- 試験はシステム上で自動配信・タイマー管理
- 必要に応じて合格証を自動発行
Step5|試験結果の分析とアフター対応
試験終了後は、受験者のデータをもとに結果分析を行います。
- 問題ごとの正答率の確認
- 難易度の調整や問題の見直し
- 合格率や平均点からのフィードバック
これらを次回試験の改善に活かすことで、試験の質や満足度の向上につながります。
また、企業内試験であれば成績データを昇進・研修計画に活用するなど、試験結果を戦略的に使うことも可能です。
オンライン試験の導入は“仕組み化”が成功の鍵
オンライン試験は、導入後の運用までを見越して計画を立てることが重要です。
「システムを入れただけ」で終わらせず、試験運営全体をどう“仕組み化”するかを意識することで、効率的かつ安定した試験実施が実現できます。
testableのようなシステムは、こうした運用に必要な機能が網羅されており、専門知識がなくても導入・運用しやすい設計になっているため、はじめてのオンライン試験導入でも安心です。
まとめ|自社に合ったオンライン試験システムで、試験運営をもっと効率的に
オンライン試験システムは、業務効率化・コスト削減・公平性の確保といった多くのメリットをもたらします。
しかし、試験の目的や対象によって必要な機能は異なるため、システム選定の際には「どんな試験を、どのように運営したいか」を明確にすることが大切です。
testableは、研修会社や資格試験団体など、試験運営の現場に寄り添った設計がされており、CBT対応・記述式問題・LMS連携・受験者管理など実運用に必要な機能を網羅しています。
オンライン試験の導入をご検討中の方は、ぜひ一度チェックしてみてください!
