検討中のお客様へ
サービスに関する価格やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問合せください。
大学の小テストにTestable導入。不正防止機能の充実でオンライン受験でも高い満足度

大学の小テストにTestable導入
不正防止機能の充実で
オンライン受験でも高い満足度
同志社大学様
同志社大学様は、明治六大教育家の一人である新島襄が1875年京都の地に創立した同志社英学校をルーツとする総合大学です。
新島襄の教育にかける情熱を現代にいたるまでの150年間引き継ぎ、建学の精神「良心教育」に基づいた「良心を手腕に運用する人物」を養成し、経済・政治・宗教・教育・社会事業など、多方面で 活躍する人物を広く社会に送り出し続けています。
2020年以降、コロナ禍によってオンライン授業の需要が急速に高まり、評価手法として主流だったレポート課題には、学生の負担が大きいことや、生成AIの普及により公正な評価が難しくなるといった課題が浮上していました。
そうした状況の中で、オンライン上でも公平かつ効率的にテストを実施できる手段を模索されていた同志社大学様に、「Testable」をご導入いただきました。
今回は、導入に至った背景や課題感、実際にご利用いただいた後の学内での反響、そして運用面での変化について、詳しくお話を伺いました。
プロシーズ側(以下P) ── オンライン試験を導入しようと思ったきっかけを教えて下さい。

同志社大学様(以下D) 大きく3つの理由があります。
1つ目はコロナ禍の到来によりオンライン授業が増加したことです。オンライン授業では、対面での授業のように学生の反応を把握するのが難しくなります。こうした状況の中で、学生の理解度を把握する手段として、毎回小レポートを課す授業が増加しました。しかし、レポートが増えれば、学生はこれまで以上に執筆に追われることになりますし、教員も採点の工数が増加します。
そして、こうした工数の増加とともに課題となったのが、2つ目の信憑性です。成績評価をレポートに依存する授業が多くなる中で、「本当に本人が書いたのか分からない」という問題が浮上しました。
3つ目には、「多面的な評価」の重要性が教育現場でも重要視されるようになってきたことが挙げられます。レポートだけでなく、知識を問うような課題等、多面的に取り入れることが求められます。オンライン試験の導入は、そうした多面的な評価の一助になると考えました。
このような背景から、オンライン試験の導入を検討し始めました。
P ── オンライン試験の導入には一定のラインを設けていたと伺いました。
D 基本的に定期テストには導入せず、レポートの代わりとなる小テストにオンライン試験を採用しました。また、600人以上の受講者がいる授業のみを対象にしています。
P ── 数あるオンライン試験システムの中からTestableを選んだ理由を教えて下さい。

D 最も大きな要因は、顔認証や監視機能など、不正行為を防止する機能が充実していたことです。
また受験者側の設定や準備が簡単であることや、ユーザーインターフェースの良さ、導入後のサポートの手厚さも、導入決定を後押ししたポイントとなっています。
実際に他社のサービスとも比較しましたが、監視機能や操作性の良さなどから、Testableを選んでいます。
P ── ありがとうございます。スムーズな導入のために独自の取り組みを行ったと伺いました。

D 2つございます。
1つ目はTestableを利用する前に視聴する解説ビデオを独自に作成していることです。小テストの作成の手順や操作確認のための練習問題などを用意しています。
2つ目が、一部の科目での実施になりますが、不合格になった場合、合格するまで何度でも受験できるようにしていることです。Testable導入によって、受験直後に合否がすぐにわかるようになりました。そのため、合否結果に合わせて再受験できるように設定しています。
P ── Testable導入後はどのような効果を感じていますか。

D 教員からは「Testableの受験後の点数表示や合格不合格機能を有効に利用できる」と好評です。というのも、オンライン試験を導入する前からオンデマンド授業を導入していましたが、どうしても教員から一方的に情報を伝える状況になっていたという課題がありました。しかしTestableでは、採点結果を個別にフィードバックができ、さらに何度も受験できるので、学習効果が高まったという声が教員から多数聞かれています。
学生からは、いつでもどこでも受験できる点や進捗率が表示されるようになったことなどが好評を博しています。
さらに当初懸念していた、レポート増加による学生と教員両方の負担も軽減できたことや、公平かつスムーズな試験実施が可能になったこと、問い合わせ件数が担当者一人でも対応できる数だったことも良かったですね。
P ── 今後プロシーズに期待することを教えて下さい。
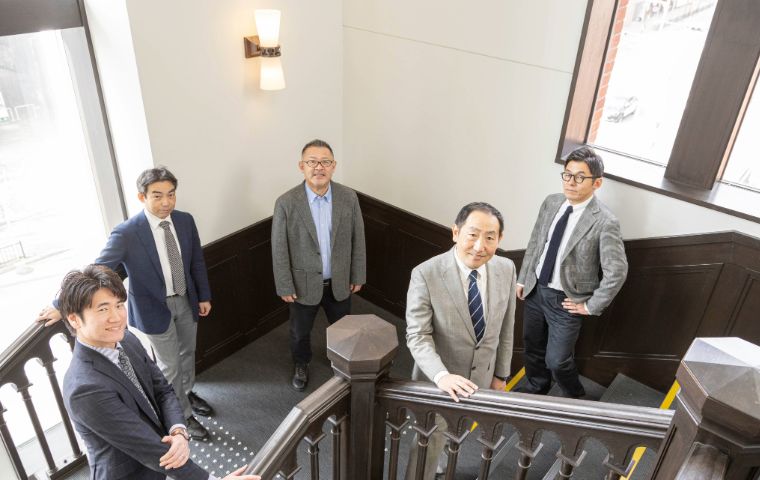
D 生成AIを活用したレポート採点機能や、高度な分析ツールなどの開発を期待しています。
P ── ありがとうございました。これからもご期待に添えるよう、引き続き取り組んでまいります。