売れるオンラインスクールの作り方とは?機能やサービス、流れまで徹底紹介
- 2022.06.13
- コラム


オンラインスクールを作りたいものの、何が必要なのか、どんなサービスを利用すればいいかわからずお困りではありませんか。
オンラインスクールを構築・提供するためのサービスは多岐にわたりますが、基本となる機能は共通しています。だからこそ、オンラインスクールを比較したときに何を選べばいいのかが分かりづらくなっています。
一方、初心者であっても、目的にあったオンラインスクールシステムを選び、ポイントを押さえて作成することで、クチコミで選ばれるような継続性のあるサービスを作り出すことも可能です。
そこで今回は、クチコミで選ばれるオンラインスクールの作り方のポイントや、サービスの選び方についてご紹介します。
オンラインスクールとは?
オンラインスクールとはインターネットを介して受講できるレッスンや講座などのことです。動画配信やオンライン会議が手軽にできるようになり、より一層注目を集めるようになりました。
英会話やWEBデザインといったものから、ピアノやヨガなど技能を学ぶものまで、オンラインスクールにはさまざまな種類があります。
オンラインスクールのメリット・デメリット
講師から見たオンラインスクールには以下のようなメリットがあります。
<オンラインスクールのメリット>
- 離れた相手にも授業ができる
- 三密を防ぐことができる
- スマホなどでも受講できるため受講いただける機会が増える
<オンラインスクールのデメリット>
- 同じ場所にいないので受講者の温度感が図りづらい
- 直接会わないので受講者のモチベーションが下がりやすい
- 複数人に受講いただく際の個別フォローが難しい
一方で、オンラインスクールの作り方を工夫したり、既存のサービスを利用したりすることで、デメリットを解消できる場合もあります。そのため、提供前に必要な機能や便利なサービスをチェックし、全体設計を考えていくことが、オンラインスクールそのものの質を大きく左右することになるでしょう。
また、すでにオンラインスクールを作っているものの課題を抱えている方は、上記のポイントを見直すことで、収益や集客を改善できる可能性もあります。ぜひ一度以下の内容をチェックしてみてください。
オンラインスクールを作るために必要な機能
オンラインスクールは教材と配信ツール以外にも、さまざまな機能が必要です。ここではオンラインスクールに必要な要素を確認していきます。
集客ツール
オンラインスクールに限らず、ビジネスには集客が不可欠です。教材を準備するだけでなく、申込みに至るための集客用コンテンツを用意しておきましょう。
具体的には集客(広告)用のホームページやSNSなどが該当します。他にも、講座受講プラットフォームや動画配信プラットフォームなど、親和性の高いオンラインサービスを利用するのもおすすめです。
会員管理・予約システム
オンラインスクールでは、複数人の受講者とのやりとりが発生することもあるでしょう。受講者の授業進捗や予約対応、入金管理やその後のフォローなど、必要な業務は多岐にわたります。
アナログや自前のシステムで対応することもできますが、受講者が増えるほど運用が難しくなるものです。顧客対応の滞りは、受講者のモチベーションを下げる原因になります。
円滑に対応するためには、会員管理や予約に特化したシステムやサービスの導入が必要です。サービスを選ぶ際には、以下のポイントを確認しておきましょう。
<会員管理・予約システムを選ぶ際のポイント>
- 講師が開講日を指定でき、受講生が自分の都合に合わせて開講日の予約ができるか
- 受講の進捗管理ができるか
<付随していると便利な機能>
- 多様なオンライン決済と支払い方法
- 教材配信機能
- メール送信機能
- リマインド機能
- 割引や無料会員制度など本会員以外の機能
必ずしもすべてを揃えておく必要はありませんが、システムを選ぶ際のポイントとしては押さえておいたほうが良いでしょう。
教材配信ツール
オンラインスクールでは、動画や資料などを受講者に送付する機会も少なくありません。メールやコミュニケーションツールでも対応できますが、メールが自動配信されるツールを用意しておけば講座購入時に手動で受講生に配信方法をご案内する等の手間を省くことができます。
決済ツール
決済ツールがあると、スムーズに受講料を徴収できます。以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
<決済ツールの選び方>
- クレジットカードやQRコードなど多様な決済が利用できる
- 一括・月払い(サブスク)など多様な支払い方法が選べる
オンラインスクールが作れる主なサービス比較
続いてオンラインスクール自体を作るサービスについても確認しておきましょう。
WordPress
ホームページ作成の知識がなくても、本格的なサイトが作れるサービスです。無料でも豊富なテンプレートが用意されている他、会員管理や決済機能などを追加することができるなど、カスタマイズしやすいのが特徴です。
<WordPressでオンラインスクールを作るメリット>
- コードを書けない人でもカスタマイズが比較的手軽にできる
- 必要に応じた機能を実装できる
- デザインの自由度が高い
一方で、自分でメンテナンスやアップデートを行わなければならなかったり、ランニングコストとしてサーバー代がかかるといったデメリットもあります。また「よりよい見た目にしたい」「より機能をリッチにしたい」といった場合は、プロの力を借りたほうが良いことも。
その場合はコストが嵩むため、自分でできる範囲とどこまでカスタマイズするかを見極めた上でWordPressにするかどうかを判断したほうが良いでしょう。
Facebookグループ
SNSのFacebookには、ユーザーをグルーピングして情報発信したり情報発信したりといったことができる「Facebookグループ」という機能があります。無料で利用できる他、WordPressよりも簡単にグループを作成・管理できるため、より手軽でコストを掛けずに行いたい方におすすめです。
<Facebookグループでオンラインスクールを作るメリット>
- 普段から使い慣れているツールでやり取りができる
- 双方向のコミュニケーションが取りやすい
- 基本無料で利用可能
- イベント管理などもしやすい
一方、Facebookグループには決済機能がないため、他のツールを利用する必要があります。また、基本的にはFacebookアカウントを持っている人だけが利用できるサービスのため、それ以外の受講者の管理ができないこともデメリットと言えるでしょう。
また受講中にFacebookアカウントがなくなってしまったり、のっとり被害に遭ってしまったりする可能性もあり、セキュリティ面で不安が残るかもしれません。
LINE公式アカウント(旧 LINE@)
国内の月間利用者数が約8,400万ユーザーを超えるLINE(2020年9月末時点)。そのプラットフォームを利用し、ユーザーに情報配信やクーポン付与などを行えるのがLINE公式アカウントです。以前はLINE@(アット)という名称で親しまれていました。
LINE公式アカウントの強みは、圧倒的なユーザー数と豊富な機能です。講師のLINE公式アカウントを準備し、友だち登録してもらうことで、月1,000通まで無料で情報配信が行えるほか、ショップカードやステップ配信、チャットやテレビ電話も利用することができます。
<LINE公式アカウントでオンラインスクールを作るメリット>
- 無料で使える機能が豊富
- 圧倒的な利用者数を誇るLINEのユーザーにアプローチできる
デメリットは、相手から連絡が来ない限り双方向のコミュニケーションができないことです。LINE公式アカウントは情報配信に強いツールですが、双方向のコミュニケーションという点ではできないことも多くあります。
また、受講者によって進捗がバラバラの場合、毎回動画や資料を送付する手間がかかります。また決済サービスは付随しないため、別途用意する必要があります。
オンラインスクールパッケージ
オンラインスクールに必要な一連の機能を有したパッケージです。認知度の高いサービスの場合、すでに顧客となりえるターゲットが多数集まっているので集客がしやすいほか、月額で利用できるものが多いため、比較的敷居低く始めることができます。
<オンラインスクールパッケージでオンラインスクールを作るメリット>
- オンラインスクールに必要な基本的な機能が揃っている
- パッケージに集客できるサービスが含まれる場合、顧客を獲得しやすいことも。
一方で、月額利用料がかかるものがほとんどのため、毎月決まった費用がかかります。また海外のサービスが多いため、英語の説明に苦慮する方もいらっしゃるかもしれません。
そのほか、ご自身の展開される教育分野によっては競合が多い場合もあります。既にたくさんの競合他社がコストをかけて集客している場合が多く、後発での参入の場合には集客に苦戦する可能性もあるでしょう。
いずれもメリットとデメリットがあるので、それぞれを比較した中で、どのツールを選ぶべきか判断することが大切です。
オンラインスクールの作り方の流れ
ツールの選択肢がわかったところで、いよいよオンラインツールを作る・選ぶ流れに移ります。ここからはより具体的にオンラインスクールの作り方について説明していきます。
オンラインスクールの目的やターゲット(要件)を整理する
まずは「なぜこのオンラインスクールをするのか」を細かく整理してみましょう。具体的には「目的」「ターゲット」「受講によって受講者が得られる利益」を整理します。
ポイントは受講者目線で客観的に考えることです。主観的な考えでは顧客には魅力的に映りません。「このオンラインスクールを受けなければならない(受けたくなる)理由」を、顧客目線で考えてみましょう。
必要な機能を整理しツールを検討・導入する
要件を定義できたら、それを満たすために必要な機能を検討し、ツールを選定します。先程もご紹介したとおり、ツールにはそれぞれメリットとデメリットがあります。なんのサービスを利用し、どの機能を実装する必要があるのかを書き出した上で準備すると漏れがなく安心です。
実装前には費用も合わせて算出しておきましょう。どのツールを選ぶべきか悩んでいるのであれば、イニシャルコストとランニングコスト、できることを見える化して比較するのがおすすめです。
教材を作成・アップロードする
オンラインスクールの基礎的な部分が整ってきたら、次に教材を用意します。教材の作り方については「初心者のためのオンライン講座の作り方完全解説!注意点から作成ステップ、ポイントまで」でご紹介しておりますので、合わせてご確認ください。
その他に必要なツールを準備する
教材の準備ができたら、その他に必要なツールがないかを確認します。
<忘れがちなツールまたはポイント>
- 集客用ツールまたはホームページ
- 会員管理機能
- 決済機能
- 受講者とコミュニケーションを取る方法
- 動画配信ツール
集客・販売する
環境が整ったら、広告宣伝等で集客を図ります。集客方法はSNSやWEB広告、クチコミなどさまざまですが、集客の際は自社のサービスに興味を持ってくれる層がどの方法でもっとも集客できたのかをチェックしておくと、その後の集客がより効率的に行なえます。
クチコミで選ばれるオンラインスクールの作り方のポイント
ここからは、受講者が思わず人に教えたくなるような、クチコミで選ばれるオンラインスクールの作り方についてご紹介します。
多様な支払い方法を用意する
たとえ興味があり購入意欲が高かったとしても、手に入れるまでのプロセスが面倒だと気持ちも冷めてしまうものです。また決済方法が少ないことも、購入意欲を減退させる原因になります。
一方、単価が高いサービスであっても、一括払い以外にも分割払いが利用できたり、サブスクのように月額料金で利用できたりする場合は、購入のハードルが下がる可能性も。
「受講者にとって便利な支払い方法」を選択できることは、受講者にとっても満足度が高く、クチコミにつながる要因のひとつになるでしょう。
無料会員機能や割引など購入ニーズを引き出す仕組み
顧客の中には「いきなり購入するのはハードルが高い」と思っている方も少なくありません。購入のハードルをなくすためには、有料サービスを限定的に受けられる無料会員制度を用意したり、期間限定で割引価格で購入できたりといったサービスを用意するのもよい方法です。「使い切らないと損をする」という心理がはたらき、購入を促しやすくなります。
受講後に別のコースや次の講座の購入を促すことも有効です。その場合は受講後7日以内の購入で割引が受けられる仕組みにしておくと、購入に繋がりやすくなります。
無料会員から有料会員へ誘導する仕組みを用意する
無料会員から有料会員になっていただくためには、魅力的な購入特典を提示するのが良いでしょう。最後の講座を受講してから7日以内であれば購入特典が受けられるといった特典は、その主たる例と言えます。
また、ステップメールで割引期間終了が迫っていることを伝えたり、有料会員になった場合の講座内容を少しだけ見せ、購入意欲を高めることも効果的です。こうした誘導の仕組みを活用し、無料会員から有料会員への導線をつくりましょう。
学習のモチベーションを引き出す仕組みを用意する
受講者にとっては、有料会員になることがゴールではありません。せっかく購入しても、利用しなければ意味がありません。そこから学びを深めていただくことが、結果的に受講者の利益に繋がります。また「継続しやすいこと」自体をメリットと捉え、良いクチコミが広まることも少なくありません。
継続して学習いただくためには、学習のモチベーションを高いまま維持したり、さらに引き出したりする仕組みが必要です。例えば学習後に就職先の紹介があるなど、ユーザーの利益につながるインセンティブを用意するなどが挙げられます。他にもさまざまなインセンティブが考えられますので、ぜひユーザーの利益につながる仕組みを考えてみてください。
オンラインスクールを手軽&お得に作るなら
オンラインスクールを作るためには、さまざまな機能を用意する必要があります。その点、オンラインスクール専用システム「School Launcher(スクールランチャー)」を利用すれば、必要な基本機能を一度に揃えることができます。
これからオンラインスクールを作ろうと思っている方も、現在開設しているものの、運用に問題を抱えている方も、ぜひ一度ご検討ください。
-
前の記事

【活用事例】「グレースアカデミー」(株式会社ヒトデザイン様) 2021.08.13
-
次の記事
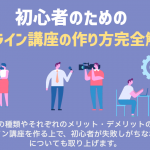
初心者のためのオンライン講座の作り方完全解説!注意点から作成ステップ、ポイントまで 2022.06.13

